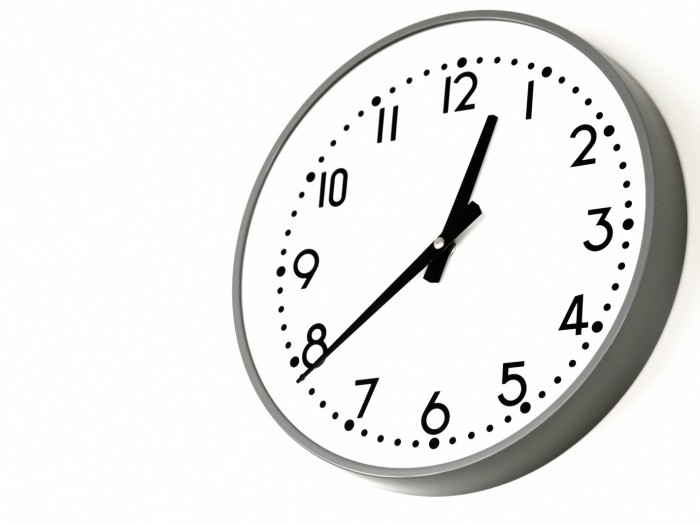企業内弁護士(インハウスローヤー)の現状
- INDEX
-
-
1.企業内弁護士(インハウスローヤー)とは?
-
2.増加傾向が顕著な企業内弁護士(インハウスローヤー)
-
3.採用企業数の推移
-
4.企業内弁護士(インハウスローヤー)でWLB(ワークライフバランス)はとれるのか?
-
5.企業内弁護士(インハウスローヤー)は年収が下がる?
-
6.企業内弁護士(インハウスローヤー)の仕事の領域、顧問弁護士との違い
-
まとめ
-
1.企業内弁護士(インハウスローヤー)とは?
一般企業に所属する場合は、当該企業の業務分野に即した企業法務案件やコンプライアンス体制強化などの業務を中心に扱うことになります。また、官公庁などに所属する場合は、法令の制定、市民相談への対応、教育委員会・社会福祉協議会などの関係機関との連携など、幅広い分野への対応が求められることも多いようです。
2.増加傾向が顕著な企業内弁護士(インハウスローヤー)
また、2001年には企業内弁護士に占める女性の比率は19.7%でしたが、2020年には40.7%にまで増加しています。2020年の弁護士全体における女性比率は19.1%ですので、組織内弁護士(インハウスローヤー)として活躍している女性弁護士の割合はかなり多くなってきています。
3.採用企業数の推移
なお、同月における「企業内弁護士を多く抱える企業」の上位20社には、三井純友銀行(3位・24名)、三菱UFJ銀行(8位・20名)、みずほ証券(18位・13名)などの銀行系、双日(8位、20名)、丸紅(11位、19名)、伊藤忠商事(18位、13人)のような老舗企業のほか、ヤフー(1位、39名)、LINE(2位、26名)、アマゾンジャパン(5位、22名)のように1990年代以降に設立した会社も多くランクインしています。
4.企業内弁護士(インハウスローヤー)でWLB(ワークライフバランス)はとれるのか?
一般的な法律事務所では、弁護士と業務委託契約を交わしています。つまり、所属弁護士は「労働者」ではないので、労働基準法や労働契約法による保護は受けることができません。
他方で、組織内弁護士の場合、雇用契約を企業と直接交わすことになるので、労働法上の保護(例えば労働時間、各種保険制度の適用、年次有給休暇の取得など)を受けられます。
また、政府が推し進める働き方改革で、長時間労働の是正、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備(テレワーク、副業・兼業など)、ダイバーシティの推進(女性が活躍できる環境整備、子育て・介護などと仕事の両立など)が進むと、さらにWLBがとりやすい環境になることが想定されます。次の項目でも詳述しますが、実際、法律事務所に所属している場合と比べて、組織に所属したほうが、福利厚生や産休・育休制度が充実している場合も多く、結婚や出産を機に組織内弁護士(インハウスローヤー)としての道を選ぶ弁護士も少なくありません。
関連コラム『弁護士はどうやってワークライフバランスを確保すべきか?』
5.企業内弁護士(インハウスローヤー)は年収が下がる?
企業においては、単純に弁護士資格を保有していることだけでなく、業務に対しての即戦力性や年齢及び社会人経験年数などを踏まえた上で、他の社員の年収とのバランスを意識して収入を決定する場合も少なくありません。法律事務所勤務時代よりは、年収が下がるかもしれませんが、弁護士の場合、同年齢の一般社員よりは高く設定されていることが多く、弁護士会費も85%の会社では企業負担です。※前出のJILAアンケート調査より
JILAのアンケート調査によると、組織内弁護士(インハウスローヤー)の年収(支給総額)は500~750万円未満22%、750~1000万円未満28%、1000~1250万円23%となっています。これを経験年数別にみると、弁護士経験5年未満の人は、54.5%が年収500~750万円未満ですが、弁護士10年~15年未満になると、40.6%が1000~1250万円未満となっています。さらに、企業で正社員として働く場合には、社会保険や各種手当などの福利厚生も付与されますので、これらも加味すれば、法律事務所で働く場合と比べても遜色のない金額といえるでしょう。
法律事務所で弁護士として働く場合は、固定給ではなく、歩合の場合も多いため、働けば働くだけ収入につながりますが、裏を返せば、成果を出して新件を受任し続けなければ収入が下がる可能性があるともいえます。定年まではサラリーマンとして安定した給与をもらえるという点は、安心につながるともいえそうです。
関連コラム『弁護士の転職ストーリー7 グローバルな取引の最前線で仕事がしたい…外資系法律事務所から大手商社グループへ転職した40歳弁護士』
6.企業内弁護士(インハウスローヤー)の仕事の領域、顧問弁護士との違い
ただ、企業内弁護士の担当業務はその企業の扱う分野の案件に限られますし、代理人となり法廷に立つ機会もあまりないと考えられます。訴訟になるような困難な案件は外部の弁護士に依頼することが多く、その場合、社内の弁護士は外部弁護士との橋渡し役に徹することになります。JILAのアンケートでも、訴訟代理人となることがある組織内弁護士(インハウスローヤー)は全体の2割程度にとどまっています。訴訟も含め、幅広い分野の案件を扱いたい方は、法律事務所で働きながら、企業法務には顧問弁護士として携わる方が合っているかもしれません。
また、法律事務所で勤務する場合は、事務所によってその程度は異なりますが、業務に対するそれぞれの弁護士の裁量が比較的大きいといえます。一方、会社は「組織」としての意思決定が大切であり、弁護士であっても、そこに所属する以上は組織の一員としてのふるまいが求められます。また、現状では、副業としての個人案件受任が制限される場合のほうが多いです。それを窮屈に感じる方は、法律事務所で勤務を続けるほうがよいかもしれません。
まとめ
データ参照元:JILA 統計・ライブラリ
弁護士として、どのような仕事に携わりたいかをイメージした上で、どのタイミングでどのような環境で働き、どんな経験を積み重ねていくか、戦略的にキャリアプランニングすることをお勧めします。
「弁護士転職.jp」を運営するC&Rリーガル・エージェンシー社では、中長期的なキャリアプランニングのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。